園では、毎月お便りが保護者の方へ配布されています。お便りの内容は、行事や子どもの達の成長、出来事、お知らせなどが記載されており、どこの園でも欠かせない物となっています。アナログからデジタルへと移り変わった園もあるかと思いますが、先生の作成は昔と変わらず必要です。
お便りを書くことは、行事が多い先生の中では悩みの1つ。色んな事を考えなければいけない上に、お便りを書くことはすごく気を遣います。
お便りの書き出し部分は、最初に目を通す部分となるので、気を遣って書くことで定型文を書いてしまいがちにななったり、文章が浮かばない・・・と悩んでしまう先生もいます。
ここでは、7月の「お便り」に使える文例と内容をまとめてみました。7月は、七夕やキャンプなどの行事があります。出来事を交えながら書いていく形がオススメです。
お便り作成がはかどるよう、以前私が作成していた内容を元に紹介します。
私が勤めていた園では、月の終わりの日に翌月のお便りを配布していました。7月のお便りは6月30日に配布し、内容は6月に行った行事の様子や、制作などを記載していました。子どもの様子も付け加えて書くことで、保護者の方が「こんなことしたんだね」と喜ばれたりするので、オススメです。
目次
お便り作成のポイント
お便りを作成のポイントは、つまり「伝えること」です。
保護者の方へ、行事や子どもの達の成長、出来事、お知らせを明確に伝わりやすい文章を心がけることが必要となります。
<POINT>
- 季節感を取り入れた書き出し文
- 季節感を取り入れたイラスト
- 伝えたい子どもの様子
- お知らせ
保護者へ伝えたい事をまず簡単に、メモやテキストボックスの中に埋め込んでおきます。それから、作成に取り掛かることでスムーズに取り組みやすくなります。伝えたいことが決まると、より具体的な内容を記入しやすくなります。
書き出しは、季節感を出して書くことで相手が共感します。しかし、定型文だけでは今の季節とは多少違う内容となることもあるので、読み手からは違和感を感じる事もあるので、その時期に合う言葉を選びましょう。
仕事で忙しく、お便りを見落としてしまう事もありますので、大事な部分は、色を付けたり、字の大きさを調整したりして、パッと読んだだけで伝わる書き方が好ましいと思います。
7月 季節感あふれる文例の書き出し
- 梅雨はまだ続いていますが、徐々に暑くなる日々が夏の訪れを感じさせる気候になってきました。梅雨にしかできない体験をして、子ども達も伸び伸びと楽しそうでしたよ。
- 園生活の環境に慣れ、子ども達はその年齢クラスに合った姿に成長しています。周りの友達の影響力は強く、同じ事を試みる姿に集団生活でのやり方を学んでいる様子がよく見られるようになり、友達や保育士と一緒に楽しい毎日を過ごしています
- 梅雨の晴れ間からは、真夏を思わせる太陽が輝いています。友達との触れ合いも多くみられるようになりました。お喋りが多すぎて、途中で保育士に声を掛けられる事もありますが…元気いっぱいに活動に参加しています。活動旺盛な子ども達は園庭に出ると、「先生、虫探ししてきます!!」とバケツを持って、虫探し開始!!色んな虫に触れながら楽しく 遊んでいます。
- これから訪れる暑い夏を元気にのりきるために、「早寝早起き!朝ごはん!」ご家庭でも規則正しい生活リズムを大切にしてください。
- 梅雨の季節は湿度が高くなりがちで体調を崩しやすくなります。熱を出したり、感染症が起こりやすくなってりします。この悪循環に負けないように規則正しい生活を送り、バランスの取れた食事を摂るようにされてくださいね。
- だんだんと暑さも日々増していき、本格的な夏の季節もすぐそこまで来ているこの頃。子ども達は、夏の訪れを今か今かと心待ちにして、大好きなプールで思いっきり遊びたい様子です。
- 梅雨の合間の天気がいい日には、駐車場の花々が綺麗な顔をたくさん見せてくれます。そして、樹木の新緑が元気いっぱいに鮮やかな色を園庭を輝かせる中、真夏の暑さを記録する日が出てきましたね。
- 笹の葉に、みんなで作った七夕飾りや、短冊に書いたたくさんの出貝事が園を明るく照らしてくれ、七夕が来る日を楽しみにしています。
- 7月は「文月」と言われており、書道の上達を祈って、短冊に歌や願い事などを書く、七夕の行事にちなんだ呼び方の「文被月(ふみひろげづき、ふみひらきづき)」が略されて「文月」に転じたという言われていました。ほかにも、稲穂が膨らむことから「穂含月(ほふみづき)」「含月(ふくむづき)」が転じて「文月(ふづき)」になったとも言われています。
- 初夏に植えた夏野菜が、梅雨の雨で徐々に大きく生育している姿を見て嬉しそうな子どもたち。今月は、いよいよ収穫の時がやってきます。
- 日に日に暑さが増す時期。子ども達は水遊びや泥んこ遊びを楽しみにしている様子です。暑さ対策はしっかり行って楽しもうと思います。
- 雨が降ると肌寒く、陽が出ると肌が焼ける暑さ。まだまだ天候の温度差があるので体温調節が難しい子どもにとっては、体調が崩しやすい時期です。感染症にもかかりやすくなてしまうので、予防をしっかりしながら保育をすすめていこうと思います。
- 窓から日差しを、ゴーヤーの緑のカーテンがさえぎってくれています。室内の温度上昇を押さえてくれる緑のカーテンは、徐々に収穫の時期となり始め、たくさんの栄養を頂こうとみんなで楽しみにしています。
- これから、ますます暑さが厳しい季節になりますので、夏バテしないように、早寝早起き、朝ご飯をしっかり摂った規則正しい生活リズムを整えていきましょう。また、外出時は帽子を被り、水分補給はこまめに取ってくださいね。
- 近年の夏は、異常気象により猛暑の気温が毎年更新されています。子ども園でも、炎天下の活動は控えますが、熱中症などを起さないよう水分補給などはしっかりと補うように努めます。暑さは、体力を消耗しますので、早寝早起きの生活リズムは、ご家庭でしっかり摂るようにお願いします。
- 眩しい太陽と空の青さに、夏の到来を感じる季節になりました。今年も七夕飾りの中で、様々な願い事が綴られると思います。みんなの願いごとが叶うといいですね。
- 梅雨明けとともに、夏の訪れを謳歌するような蝉しぐれの季節になりました。竹笹の七夕飾りに願いが綴られると、暑い夏ももうすぐだと感じます。
- 今年は、数年ぶりに活動範囲が広がりかつての日常に戻りつつあるようです。皆それぞれが、お互いの健康を守る行動はこれからも続けながら過ごされてくださいね。
- 今年も厳しい暑い夏になるかと思いますが、楽しい夏を過ごせるようにしていきたいと思います。
7月の書き出しの文例は、夏の始まりの様子や行事などを取り入れながら書いていくと読み手が共感し、季節を感じることが出来ます。
クラスの活動内容や行事
クラス便りや園だよりでは、内容は別の事を記載します。園だよりに載せないクラス内の活動報告を記載しましょう。テキストボックスをいくつか用意しておいた中に、クラスの目標や、今月の歌、今月の活動などを記載していきます。
日頃の、クラスでの生活や活動(制作や体験)に関する事や、行事の準備をしている内容、または実施した様子やその後の事を感想として載せてもいいです。
ただし、行事予定などの内容は、別紙で詳細することが一般的です。
<7月>
七夕
- 7月7日は、子ども達が楽しみにしている年に一度の「七夕」です。七夕飾りは、一人一人色んな願いを込めながら作っていましたよ。みんなの願いが叶うといいですね。
海の日
- 7月第3月曜日は海の日、国民の祝日です。「海の恩恵に感謝し、海洋国である日本の繁栄を願う日」と制定されました。子ども達と一緒に海へ遊びに出かけたりして楽しまれてみてはいかがでしょうか?
プール
- 待ちに待ったプール開きがありました。水に怖がることは大切だという事や、命に係わるわる大事な学習である事を確認し、プールでの『約束』を行いました。
- プールが大好きな子ども達。先日のプール掃除でも、大はしゃぎ。スポンジで楽しくゴシゴシしつつも、冷たい水に触れ「ス~ッ」と、滑り込む様子の子どもが、多かったのは言う間でもありません。ですが、自分達の手でしっかり掃除したプールは綺麗になり、これからの楽しい夏の思い出を運んでくれることでしょう。
- 子ども園での最後の夏。夏が終わるころには、小麦肌に焼けた子ども達 の姿を楽しみに、これからたくさん水に触れて、楽しみたいと思います。
- お子様の命を預かっていますので、毎朝健康管理を行い、プールカードは、必ず記入をしてお持ちください。
夏野菜
-
夏野菜には、水分やカリウムを多く含んでいるものが多く、体にこもった熱をクールダウンしてくれる働きがあります。保育園の夏野菜も、すくすくと生育中。今月には、色んな食材が収穫できると思われます。トマトやキュウリ、すいか、ナス、ピーマン、オクラ、かぼちゃ…と盛りだくさんの畑の植物たち。夏に必要な栄養を摂りながら、暑いであろう日本の梅雨期と夏を乗り越えていきたいと思います。
「お知らせ」「お願い」があれば、記入しましょう
保護者の方に、お知らせしたい事があれば記入して伝えることが必要となります。先ほども伝えましたが、持ち物に関しても、大事な部分は、色を付けたり、字の大きさを調整したりして、パッと読んだだけで伝わる書き方が好ましいと思います。
7月のイラストは?
おたよりには、季節感を出した文章に加えて、イラストも季節の物を使うことが定番です。7月のイラストは、七夕、プール、海、夏野菜など。
イラストは検索するとフリー画像がたくさん見つかるので、おたよりの内容に合わせて配置を整えながら探してみてください。
まとめ
7月の「お便り」に使える文例と内容はいかがだったでしょうか?
書き出し文は、季節感を出して書くことで相手が共感します。文章を書くとき、パッと読んだだけで伝わる書き方を工夫しながら、敬語に気を付けて書いていくようにしましょう。毎月、おたよりを書いているとマンネリ化する事がありますが、その月の行事や今起きている社会現象を添えて書くことで、書き出し文は新しい文章を書くことが出来ます。
「お便り」の、書きやすい文章の参考になると嬉しいです。
最後まで読んで頂き ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
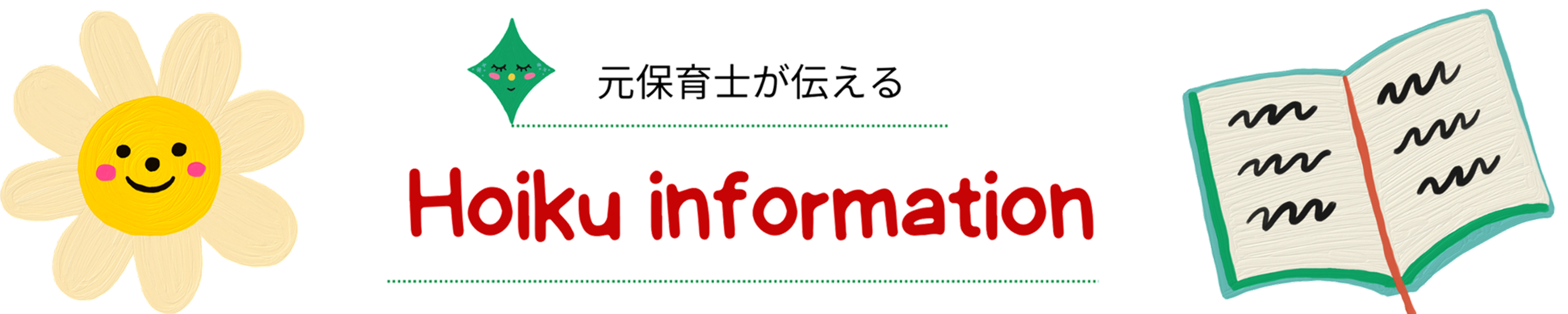



コメント