もうすぐ「七夕」ですね。「七夕」は、日本行事の1つで古くから伝わっています。
七夕が近づくと、子どもたちは「何のをお願いしようかな~」と短冊に願い事を書いたり、
七夕飾りを笹に飾ったり、わくわくしている姿が見られます。
七夕は、「彦星と織姫が1年に1度会える日」と伝えられていますね。
七夕について説明する時、難しい言葉で伝えてもうまく子どもには伝わりません。
子どもが興味を持って、「七夕」の行事を楽しめるようにお伝えしていきますね。
目次
七夕ってなに?


<七夕>七夕は、日本の一年間の重要な節句をあらわす「しちせき」の事を示しています。
そんな、難しい言葉で伝えても

子どもには、難しい言葉なので伝わりません。
次のように、
「7月7日」彦星と織姫星が一年に一度だけ夜に、天の川を渡って出会うこと。
(チャレンジ小学国語辞典より)
子どもに分かりやすい言葉で言い換える事が大事です。その時、小学国語辞典が子どもにとって、一番説明がわかりやすいのです。
その後、七夕の説明をすると子どもたちは自然と

「なんで?」「どうして?」と、疑問を持ち始めます。
子どもたちが、興味を持ち始めたところで、由来について話していきます。
七夕のはなし
昔、天の神様の娘「織姫」は、きれいな機(着物)織って人々に幸せをわけていました。
けれど、毎日機織りばかりしている「織姫」に、そろそろ結婚してほしいと、
天の神様がお婿さんを探して連れてきました。
その連れてきた人が牛のお世話をしていた「彦星」だったのです。「織姫」と「彦星」は、お互い一目で好きになり結婚しました。
毎日、2人は遊んでばかりで、「織姫」は機織りをしなくなり、
みんなの着物はボロボロのまま、
「彦星」は牛のお世話をしなくなったので、
牛は栄養がなくなって立つことさえもやっとの姿になっていきました。それを見た、天の神様が
「お前たち、働かないのであれば天の川を挟んで別々に、過ごしなさい」と、2人を天の川を挟んで別々にしました。
織姫は、毎日泣くばかり。彦星も泣くばかりでお世話をしませんでした。その様子を見て、天の神様は
「毎日、織姫は機織りをするならば、彦星は牛のお世話をするならば、
1年に1度だけ7月7日の夜に天の川で会うことを許そう」と、言ってくれたのです。
それからは、織姫は機織りの仕事を。彦星は、牛のお世話を毎日頑張ったのです。そして7月7日の夜、2人は天の川で年に1度だけ会うことが出来るようになりました。
しかし、その日が雨だった場合は川の水が増えて渡ることが出来ません。
すると、そんな2人の姿を見かねたカササギの群れが翼を広げて、
織姫と彦星が天の川を渡れるように橋となって会わせてくれるのです。
物語を子どもに分かりやすいように、要約して話すようにしてくださいね。
説明する時、棒読みではなくアレンジしながらお話しましょう。
「どうやって話したらいいの?」
「どうやってアレンジするの?」と思う方もいるかもしれません。
説明する時、いかに自分に気を引いてくれるかが、保育進行するにあたって重要です。
子どもは、面白おかしく進行するとすぐに興味を示します。
オーバーリアクションが何よりも子どもの笑いのツボに入るのです。
大人が笑うツボと、子どもが笑うツボは違います。
ちょっとしたオーバーリアクションの話し方で、とても喜びますよ。
「道具を使って話すこともおすすめ」
「道具を使って話すこともおすすめ」です。
道具とは、パネルシアターや指人形。紙芝居や、一人芝居など。
あらかじめ、小道具を用意してお話をしていくのです。
お話が大好きな子どもたち。行事の時は、ひと工夫してみてくださいね。
竹と笹について

「七夕」と言えば、欠かせないのが「竹」と「笹」ですね。


どうして笹の葉に飾るの?
昔も、今ほどではないけれど夏は暑く、暑さで食べ物が腐りやすかったのです。
昔は、今のように冷蔵庫とかもなかったからですね。
そこで腐らないように食べ物を保管していたものが、「笹の葉」だったのです。
竹や笹は、雨風にも強く、真っすぐ天に向かって1日でぐーんと大きく伸びていきます。
なので神様に見つけやすいとも言われています。
そのパワーが神秘的ともいわれていたので、短冊や七夕飾りを笹や竹にかざるのですよ。

竹と笹は違うの?

竹と笹は、見た目だと似ていてよくわかりませんよね。
春の旬な食材「たけのこ」は、この七夕の時に使用する「笹」なのです。
竹と笹の違いを、簡単に表しました。
| 成長すると | 「たけのこ」の皮 | 枝 |
| 竹 | 皮は落ちる | 2本 |
| 笹 | 茎の節に残る | 5本 |
笹は一か所からたくさんの枝を出しているので、見分けつきやすいです。
もちろん、竹や笹どちらに飾ってもOKです。
飾りたいけど、狩りに行けない・・・
今の時代、なかなか山へ竹や笹を狩りに行くことが見られなくなってきています。
竹や笹は、飾りつけの時はきれいだったのに、いざ「七夕会」をする時には、
枯れてしまうなんてこともありますよね。
そんな園や家庭には、「造花の竹や笹」
サイズ、種類と飾る場所によって選べます。
様々な種類を探してみてみてください。![]()
短冊や、七夕飾りの意味



短冊はなんで書くの?
昔の人は、「織姫のように機織りが上手になり、上達しますように」と
上手になりたいと思うことを、紙に書いてお供え物一緒に七夕の日に川に流していました。
昔は、今のように紙が当たり前に存在していなかったから、紙は高価で大切だったのです。
その大切な紙に、1番の願い事を書いて、「笹」に吊るすと
真っすぐ天に向かって伸びる「笹」が、天へお願い事を届けてくれていたと言われています。
七夕飾りの意味は?

七夕飾りは、色々ありますよね。子ども達も、協力して作り楽しんでいます。
七夕飾りの願いは、それぞれの飾りにより異なります。
どんな意味が込められているのかを知ることで、もっと七夕を楽しむことが出来ると思います。
では、1つ1つこどもに分かりやすく簡単にお伝えします。
- <彦星、織り姫> いつまでも幸せに愛しあえますように
- <吹き流し> 裁縫が上手になりますように
- <提灯> ずっと明かりを照らしてくれますように
- <短冊> やりたいことが上手になりますように
- <折り鶴> 鶴は長生きを表す鶴を折って、長生きしますように
- <網> 海の魚がたくさん獲れますように
- <屑籠> ゴミを拾ったり、物を大切にして粗末にしませんように
- <巾着> お金が貯まりますように
- <食材> ご先祖さまへのお供え物
- <紙子>病気や厄などの悪い物を代わりに引き受けてくれる
- <輪飾り> みんながいつまでも繋がっていますように
- <三角、四角飾り> 裁縫が上手になりますように
七夕飾りには、色んな願いが込められています。1つ1つの願いを知ることで、
作る意味も変わってくるので、願いの意味を話してあげることをおすすめします。
<七夕飾りの折り紙>
おりがみクラブさんより「七夕」の折り紙をピックアップさせていただきました。
子どもと一緒に折ってみませんか?
クリックすると、見ることが出来ます。
~おりがみクラブさんより~
子ども達も喜んで取り組む「折り紙」忍耐力や集中力、思考力や想像力が養われます。折り紙には、様々な図形が描かれ難しさも感じますが、手先のトレーニングになり自分なりの工夫の仕方を学ぶことができます。空間知能力も育まれ、遊びながら身に付いていくことができます。折り紙をとおして、人とのコミュニケーション力も育まれます。
まとめ
「こどもに分かりやすい七夕」についていかがだったでしょうか。
「七夕」について、子どもたちに話をする時、言葉をアレンジしながら
子供向けに話をしていくことで、子どもが興味を引き寄せます。
日本の行事が薄れがちである現在。
しかし子どもたちは、行事に積極的に楽しく取り組む姿勢は今も昔も変わりません。
だからこそ日本の行事を、令和時代の子ども達にも伝えていきたいですね。
夏の行事「七夕」。1つ1つの願い事の意味を知らせて、みんなで作ることを楽しみ、
願い事を書いた短冊と七夕飾りで、彩りを添えてあげてください。
子ども達の、わくわくした取り組みが「生きる」を養うことが出来ます。
***7月7日、みんなの願いが叶いますように***
最後まで読んで頂き ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
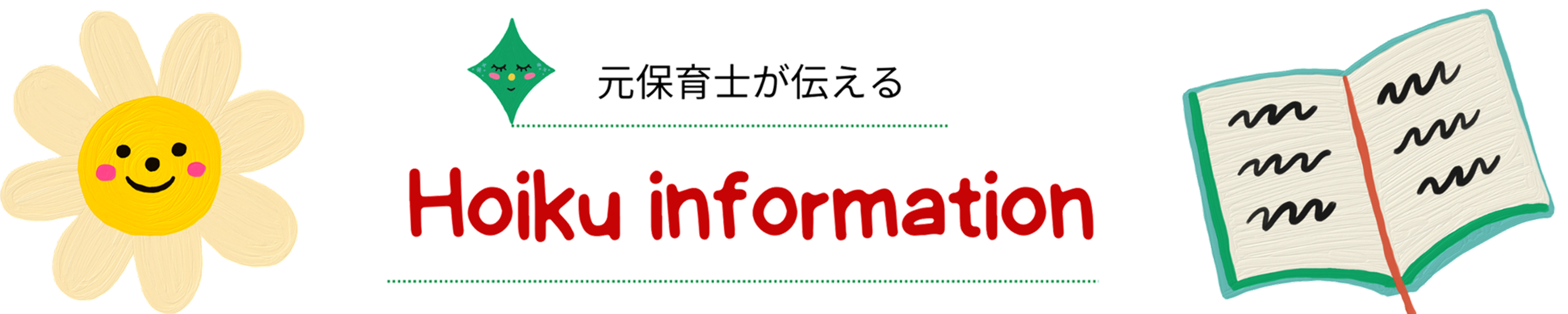



コメント