以前は、9月は台風上陸などの天災が多く発生していたのですが、今では時期は関係なく突然、私たちの日常を一瞬にして襲ってくる恐ろしい災害が、発生しています。
そこで、いざという時のために、防災の日についての知識を深め、防災対策を見直してみようと制定されたのです。
ここでは子どもに、「防災の日は何するの?」と聞かれたときに、きちんと答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるように、「防災の日」についてご紹介します。
目次
防災の日とは

日本では、昔から地震や津波、台風や豪雨などの自然災害が発生していました。そのために、災害に対する知識を深めようと1960年(昭和35年)に、内閣の閣僚了解により、「防災の日」が制定されたのです。
防災の日はいつ?

防災の日は、毎年9月1日です。
毎年9月1日ですが、この日から1週間を「防災週間」と制定されており、地方公共団体で防災の知識を高めたり、防災訓練やイベントなどが行われています。
防災の日が制定されたわけ

1923年9月1日に、“関東大震災”が起き、莫大な被害が起きました。
この地震では、たくさんの住む場所が奪われ、多くの人が怪我をしたり、亡くなったりもしました。いざという時の為に、避難する知識をえておくための防災の日と言われています。
また、この時期に、多くの台風が発生するとも言われており、台風に備えるためとも言われていたのです。
防災について話し合おう

いつ起きるか分からない災害のため、いざという時に備えて防災対策をしておかなければなりません。
子ども達と、どんな災害がおきるのか、どのように避難したらいいのか、その災害でどのような被害が起きるのか、何度も話し合い、避難訓練をする事が大切です。
自分の命は自分で守ろう

ある日突然襲ってくる災害は、誰も予想することは出来ません。
そのために、いざというために備えて防災対策をしておくことが大切なのです。
災害に備えて、防災について学んだり、バザードマップや防災マップを見たり、防災グッズの確認をしたりしていつ起こるか分かない災害について、もう一度確認しておきましょう。との意味が含まれている「防災の日」。
自分の命や子どもの命を守るためにも、繰り返し話し合ったり何度も避難訓練をすることが大切です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
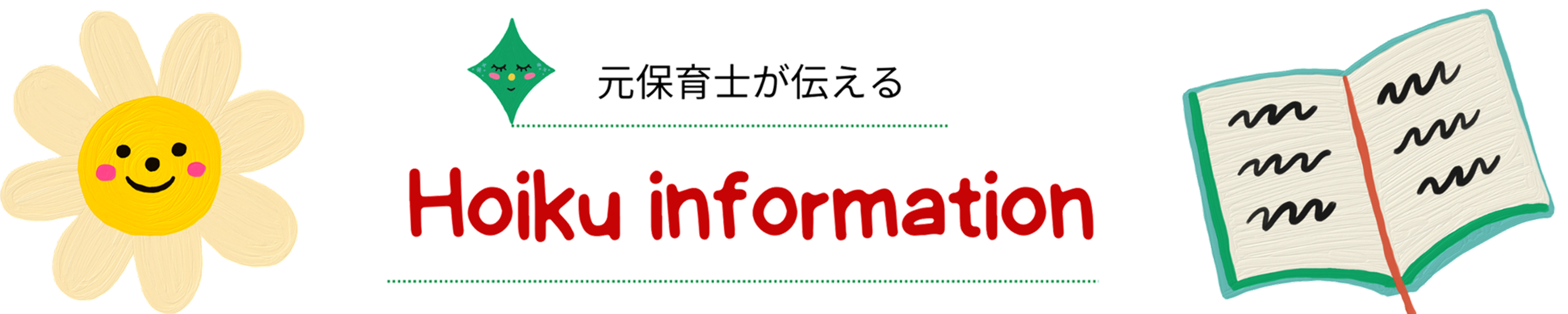



コメント