毎年、夏が来るとスーパーには「土用の丑の日(どようのうしのひ)」と店頭にキャッチコピーが並び、たくさんの鰻を目のあたりにした方も多いのではないでしょうか。
でもどうして「土用の丑の日」とあるのでしょうか。
ここでは子どもに、「土用の丑の日は何するの?」と聞かれたときに、きちんと答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるようにここでは、「土用の丑の日」についてご紹介します。
目次
土用の丑の日とは

日本の近年の夏は、猛暑日が続き夏バテになり食欲が落ちたりする方もいます。そんな時に、栄養がある「う」が付くうなぎや梅干しなどを食べて、夏バテを予防しようとといいと言われて「土用の丑の日」があるのです。
「土用(どよう)」とは、年に4回ある立春、立夏、立秋、立冬前の18日間(または19日間)を指す雑節。夏の土用は梅雨明けや大暑に重なり体調を崩しやすいため最も重視されるようになったといわれています。
土用の丑の日には「う」が付くものを食べる。

年々に猛暑日が続き体調が崩しやすい夏は、土用の丑の日にビタミンや疲労回復、食欲増進に効果的な、「う」が付く食べ物が良いといわれています。
- ウナギ:ビタミンや疲労回復、食欲増進
- ウリ(胡瓜、西瓜など):夏が旬の瓜類は、栄養価が高く、ビタミンも豊富
- 梅干し:疲労回復や免疫力アップ、新陳代謝を活発にする。
- うどん:消化吸収に優れているので、喉ごしがよく食べやすい。
- 土用餅:土用餅には厄除けにいい小豆が使われるため、食べると元気になる。
江戸時代から行われている土用の丑の日に食べる食材は、どれも栄養価が高い、または食欲がなくても食べやすい食材ばかりなのです。
夏バテ防止をしよう

暑さで食欲が落ちがちな夏の土用の日。その丑の日には「う」のつく食べ物で夏バテ防止や疲労回復、免疫力を上げてたっぷりと栄養を蓄え元気に夏を乗り切ってくださいね。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
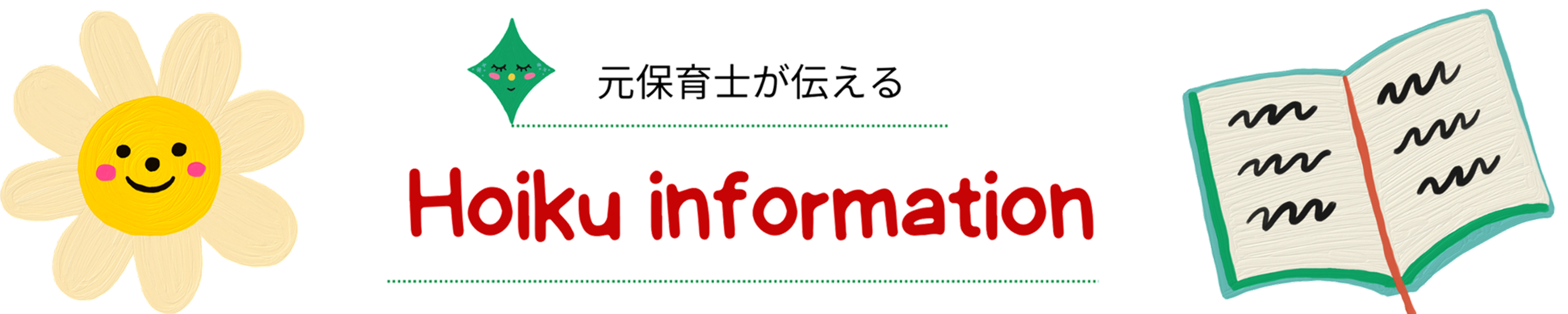

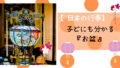

コメント