古くから日本は、行事を大切に執り行っていました。
お正月の間、年神様の居場所は鏡餅。年神様がいる松の内(1月1日~7日)は、飾っておくことがいい言われています。その松の内が終わると、鏡開きを各地域で行われています。
ここでは子どもに、「なんで鏡開きをするの?」と聞かれたときに、きちんと答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるように、「鏡開き」についてご紹介します。
目次
鏡開きとは

お正月の松の内が明けてから、お供えの鏡餅を木槌で割って食べることを、「鏡開き」と言います。
年神様の依り代(よりしろ…神様がよりついいた場所のこと)には、年神様の魂が宿っている。
松の内が過ぎたら鏡餅も下げて食べることで、年神様の力を授けてもらい、1年間の無病息災や良運を願います。
鏡開きはいつ?

鏡開きは、毎年1月11日。
地域よっては違う日にちもあるそうです。
鏡開きで年神様を見送り、仕事始めをする区切りをする意味もありました。また、剣道では新年の稽古始めに鏡開きをしてぜんざいを食べている事は、その名残であることだそうです。何気に、食べていた鏡餅にもしっかり意味があったのですね。
鏡には神様の力がある

鏡には、神様の力があるとされており、お正月にお供えする餅は、鏡のように丸いので、鏡餅と言われているそうです。
まとめ

鏡開きについてはいかがだったでしょうか。
鏡餅には年神様の力を授けてもらい、1年間の無病息災を願う行事とされています。
ぜひ、子どもと一緒に鏡開きをして、おいしいお餅を食べてみませんか?
今年、1年が幸せでありますように。
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
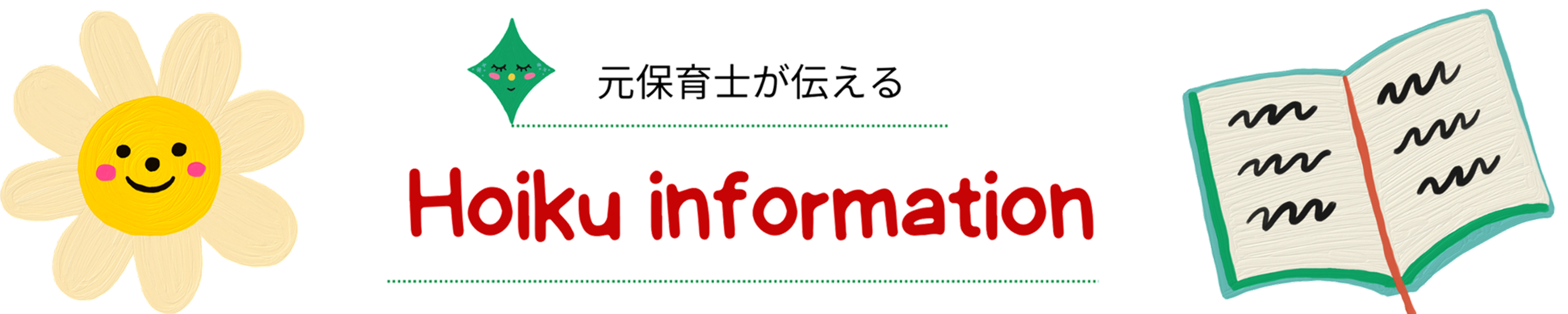



コメント