古くから日本は、行事を大切に執り行っていました。
正月が終わると、日本では昔から七草粥を食べる風習が今でも残っています。小さいころ、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ・春の七草」と暗唱してたりした方もおられるのではないでしょうか?今では、春の七草をリズムよく唱えながら覚えている子ども達です。
ここでは子どもに、「なんで七草粥を食べるの?」と聞かれたときに、きちんと答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるように、「七草」についてご紹介します。
目次
春の七草とは

春の七草は、1月7日の朝に「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」をご飯と一緒にお粥にして食べる七草粥のことです。
1月7日は「人日の節句(じんじつのせっく)」

1月7日は「人日の節句(じんじつのせっく)」と言われ、日本の5節句の1つなのです。
<五節句>
3月3日:桃の節句(もものせっく)
5月5日:端午の節句(たんごのせっく)
7月7日:七夕の節句(たなばたのせっく)
9月9日:重陽の節句(ちょうようのせっく)
奇数日と奇数日を足すと偶数になることは縁起が悪いとされていたため、邪気を払うためにこの「五節句」は、昔から大切にされてきました。
また、1月1日~1月7日の「松の内」の最終日。お正月にたくさんの美味しいご飯を食べたりした胃を休ませようと、身体に優しい粥を食べるとも言われていました。
七草とは

春の七草には、無病息災の願いが込められていたり、縁起物にされている食材がふくまれているのです。
- セリ:「競り勝つ」という意味をかけて、縁起物にされている食材
- ナズナ:なでることで汚れを払うこと
- ゴギョウ:仏さまのこと
- ハコベラ:「子孫繁栄がはびこる」として、縁起のよい植物
- ホトケノザ:仏さまがゆったりとすわっていること
- スズナ:神様を呼ぶ鈴のこと
- スズシロ:大根のことで、その根は「清らかで汚れのない純白さ」
七草粥は、地域によって食べ方も様々です。手に入らない食材は、代用して縁起のいいものを使って食べています。
お正月で美味しいご馳走を堪能したあと、ビタミン補給や胃を休め、これからの1年を元気に過ごせるようにとの願いを込めて七草粥を食べているのです。
1月7日は胃を休めよう

春の七草についてはいかがだったでしょうか。
春の七草にはたくさんの縁起物が込まれており、昔の人々が残してくれた無病息災への健康を願っての食材だったと言えます。
春の七草の意味を子どもに伝え、1月7日は身体に優しい七草粥を頂いて、1年を健康に過ごされてくださいね
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
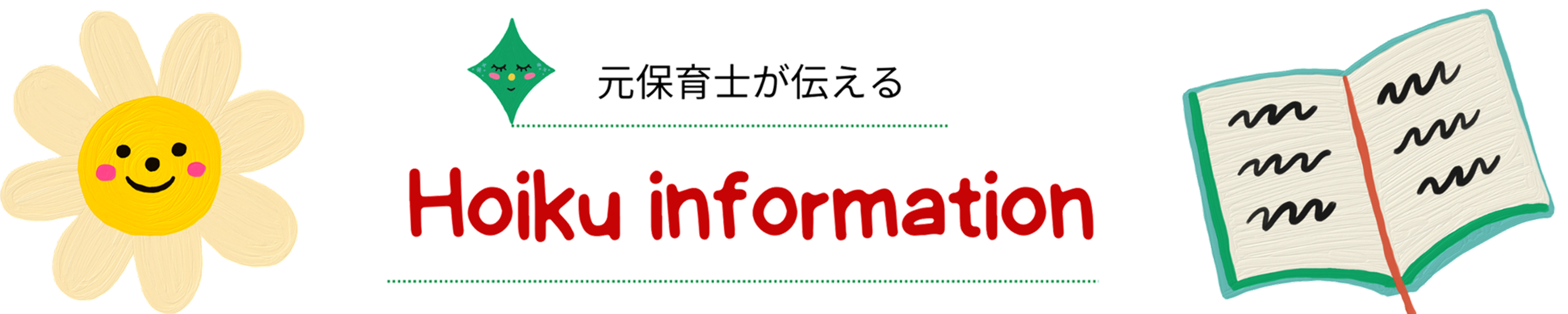



コメント