「お正月」は、一年の始まりのの大切な日。
新しい年の始まりは、誰にとっても大切な日。
どうして、この日が大切な日になるんだろう。
子どもに、聞かれたときにしっかりと答えることができますか?
ここでは、昔から日本の風習として受け継がれているお正月について、子どもにも分かりやすく伝えれるように紹介します。
目次
お正月は毎年【1月1日】

お正月(しょうがつ)は、一年の最初の日のこと。
| 1月1日の午前中 | 元旦 |
| 1日~3日 | 三が日 |
| 1日~7日 | 松の内 |
1月1日~7日までのことを「お正月」と呼んでいます。
お正月の由来

毎年お正月は、新年の年神様をお家に招いてお祝いする行事です。
【年神様って何の神様?】
年神様とは
昔は、穀物(米や麦など)のこと登志(とし)と呼んでいたことから、穀物の収穫の周期を「年」と呼ぶようになったそうです。
日本は古くから、稲作が生活の中で重要だったため、農耕の神様が年が変わると共に高い山から下りてきて、1年の幸せを守るために、正月の松の内に宿ると言われていたとのこと。
年神様は、稲作が中心だった日本には欠かせない神様です。
年神様を迎えるために、正月飾りを飾って、鏡餅やお節料理、お年玉などを用意するのです。
どうしてお正月飾りは大切なの?
お正月に、その年の福や徳を司る「歳徳神」(その年の恵方の方角にいる神のこと)や、穀物の神様が各家庭を訪れると言われています。
そこで、年神様を招くために各家庭では色んなお正月飾りを飾っています。ここでは、簡単に子どもに分かるようにお正月飾りについてまとめてみました。
門松

門や、玄関前に飾る門松は、高い山から下りてこられる年神様が分かりやすように各家庭の目印とされています。
- 松・・・1年中落葉しない木
- 竹・・・成長が早く生命力が強い
- 梅・・・新春に開花する
松竹梅は、縁起がいい植物です。そのため、門松に使われています。
現在の家庭では、門松をフラワーアレンジメントとして飾る家庭も見られるようになりました。
しめ飾り

玄関に飾るしめ飾りは、神社でも見られるしめ縄と同じように、神様が宿る印です。災厄を祓うとも言われています。
- ユズリハ:子孫繁栄
- ダイダイの実:家庭が幸運
- ウラジロの葉:不老長寿・誠実
このように、様々な縁起のいい植物と一緒に飾られます。
鏡餅

穀物の神様である年神様が、松の内に宿る場所が鏡餅の上と言われています。昔から「餅」は神様に捧げる神聖な食べ物とされていて、お祝い事や祭りには欠かせないものでした。
鏡餅には古代より神宝とされ、三種の神器が供えられています。
三種の神器とは
・八咫鏡(やたのかがみ)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)
- 餅:丸い形は人の魂と同じで、神事の鏡と同じだとか。
- 干し柿:串にささった干し柿が剣に見えるだとか。
- 橙:勾玉に見立てたものだとか。
お節料理はどうして作るの?

年神様のお供え料理で、お節料理はかかせません。
お節料理は家族の幸せや、繁栄を願う縁起のいい食材が多く含まれています。
- 黒豆:黒に焼けるほどまめに働いたり、勉強したりして暮らせるように。
- 数の子:ニシンはたくさんの子どもを作ります。その子どもが数の子です。そのため子孫繁栄と言われている。
- 紅白かまぼこ:赤は魔除け、白は清浄とのこと。
- エビ:腰が曲がるほど長生きしますように。
- 伊達巻:巻物のように、知識が増えるように。
- れんこん:穴があいていることで、将来の見通しがきくように。
他にもありますが、年の初めに見た目も縁起のいい食材を取り入れて年神様に供えることで、年神様から1年の幸せを授けてもらえるのです。
お年玉

昔は、お金ではなく餅を袋に入れて、大人から子どもへ渡していたそうです。今では、現金が習慣となっていますが、以前は節日の時には必ず「餅」を用意しており、は縁起のいいもので神様に供えた餅を餅玉に分けて配っていたとのこと。
昔から続くお年玉は、大人から子供へ「健やかに大きくなってください」との願いが込められている事は、今も昔も変わらないのかもしれません。
子ども達には、感謝の気持ちを持って受け取ることを伝えていくといいと思います。
年賀状

昔から、新年には親戚やお世話になった方への挨拶に伺う習慣があったとのこと。そのため、遠方にいる方には挨拶へなかなかい伺えないので、書状で挨拶をしたことから始まったとのこと。
現在では、ソーシャルネットワークが普及し、年賀状を出す方が減ってきています。日本の風習をなくさないためにも、年賀状の書く楽しさを伝えて次の時代に残してほしいと思います。
伝承遊び

正月と言えば、伝承遊び。時代の変化と共に、子ども達の遊び方もずいぶんと変わってきましたが、伝承遊びはいつの時代も、子どものコミュニケーション能力を高めます。ぜひ、伝承遊びを楽しんでほしいと思います。
・たこあげ ・駒回し ・羽付き ・福笑い ・ダルマ落とし
・サイコロ
まとめ

お正月は、新年の幸福をもたらす大切な行事です。
次の時代へと、日本の風習を残すために1つ1つの由来を子ども達に分かるように伝えることが、大人の役目です。
子どもにも分かる説明で、日本の文化を楽まれることを願います。
ご参考になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
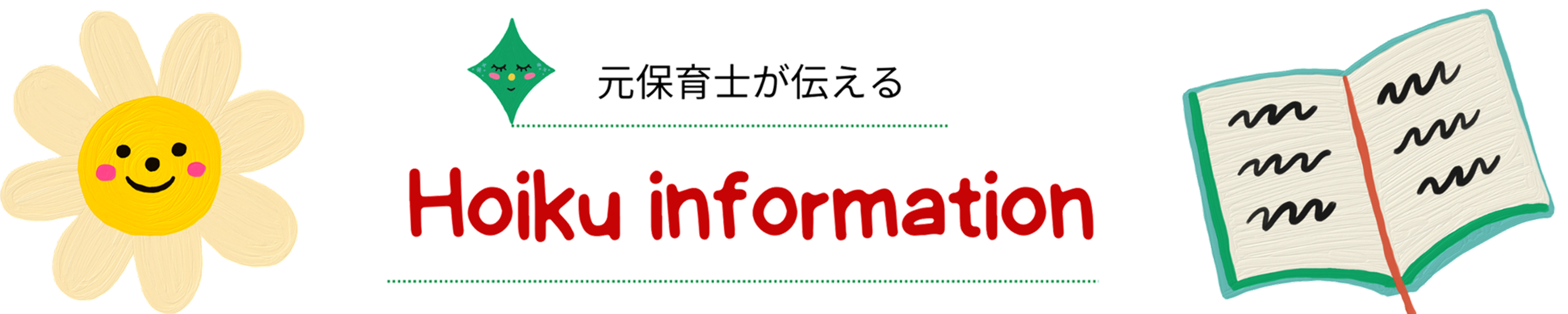

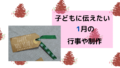

コメント