梅雨の合間にある「夏至(げし)」は、小さい頃は「まだ梅雨なのに、もう夏なの?」と思っていた私。子どもに説明する立場になった時、初めて「夏至」の意味を理解出来るようになりました。
子どもから、「夏至って何?」と聞かれたら、答える事出来ますか?
ここでは、夏至について子どもにも伝えやすくまとめてみました。
参考になると幸いです。

目次
夏至はいつ?
2021年の夏至は 6月21日頃
夏至とは、1年の中で最も太陽の出ている時間が長く、夜が短い日です。
夏至は一年で最も日が長いですが、この日を境に昼間の時間が徐々に短くなっていきます。
冬至とのお昼の長さを比べると、5時間弱も違いがあります。
夏至に食べる食材って何かあるの?
冬至には、南瓜を食べたり柚子湯に使ったりする風習が残っていますが、「夏至」にもそのような風習はあるのでしょうか?
夏至には、冬至ほどの浸透している風習は残っていませんが、一部の地域では残っている物があるそうです。
タコを食べる

関西では、タコを食べる風習が残っているそうです。
田植えが終わる頃を半夏生(はんげしょう)と呼びます。
半夏生・・・農作物を育てる目安となる時期で、夏至から数えた11日目にはじまる、5日間のことです。
タコ・・・夏至は田植え時期と重なることから、稲穂がタコ足の吸盤のように立派に実るようにと、豊作を願って。
夏越の祓(なごしのはらえ)
半年に一度の厄落としである6月の「夏越の祓」。さらに半年後の12月末には、同様に厄除けをする「年越の祓」があります。この二つは対になる行事で、心身を清めてお盆や新しい年を迎えるためのもの。

元気に夏を乗り越えられるようにと、無病息災を祈願して食べる「水無月」
見た目が涼しい「水無月」三角の形は四角(1年)の半分を意味しており、残り半年あることを示し、小豆は厄払いの意味があるといわれています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
夏至は、1年の中で最も太陽の出ている時間が長く、夜が短い日です。
日がこれから徐々に短くなっていきます。
冬至ほどの風習は残っていませんが、タコを食べたり夏越の祓を行ったりして過ごしたりされています。
夏至は、日本ならではの伝統な風習であり、これからの子ども達も残していきたい行事の1つです。
子どもにも分かる説明で、日本の文化を楽まれることを願います。
ご参考になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
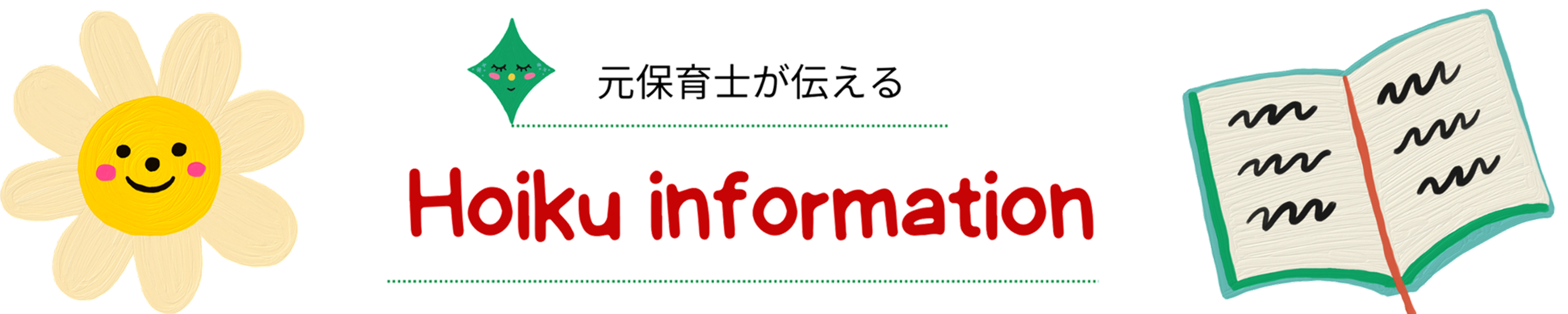



コメント