♪な~つもち~かづく は~ちじゅうはちや~♪
昔から歌われている、日本の童謡曲「茶摘み」の曲は、誰もが1度は聞いたことがある曲ではないでしょうか。
5月に入ると、新茶が出回る季節が到来します。今の時代、急須に注いで美味しいお茶を飲む習慣がなくても、新茶のペットボトルを購入したり、ショッピングモールでのお茶の香りに立ち止まったりした経験があるのではないでしょうか。
色んな行事を楽しみにしている子ども達へ、しっかりと行事の意味を伝えられるようにここでは、子どもにも分かる「八十八夜」についてまとめてみました。
ぜひ、行事の参考になると幸いです。
目次
八十八夜について

八十八夜とは、
立春から数えて88日目の日のこと。
その年よって日にちは変わります。八十八夜は、暦の二十四節気を補完するものとして、言い表されてきた雑節のひとつです。
どうして八十八夜というの?

立春は、暦の上では春ですが実際には、寒さが厳しい時期になります。その上、暦を頼って農作業をしていると霜などの思わぬ被害があったそうです。
そのため人々は長い冬を終え、春が来て天候も安定したこの頃(88日)を基準として、田植えの準備や茶摘みなどの農作業を行う時期としていたとのこと。
八十八夜に新茶を飲もう

八十八夜は、まさに「新茶」季節。
新茶=新芽を摘んで作られたお茶のこと
長い寒い冬にじっくりと栄養を蓄えた葉は、春になると少しずつ芽を出し始めます。この時期に芽吹いた葉を摘んで作ったお茶が新茶です。
その新茶には、うまみ成分や栄養が多く含まれているため新茶を飲むと、「病気にならない。長生きできる。」など言われているのです。
茶摘み

| 曲名 | 茶摘み |
| 作詞 | 文部省唱歌 |
| うた | 童謡 |
| 再生 |
なつもちかづくはちじゅうはちや
のにもやまにもわかばがしげる
あれにみえるはちゃつみじゃないか
あかねだすきにすげのかさひよりつづきのきょうこのごろを
こころのどかにつみつつうたう
つめよつめつめつまねばならぬ
つまにゃにほんのちゃにならぬ
日本伝統曲の「茶摘み」は、4拍子の子どもも歌い覚えやすい曲です。
まとめ

八十八夜についていかがだったでしょうか。
八十八夜は、古くから行われている日本の伝統行事の1つです。
昔から日本茶は、日本人に親しまれているお茶です。近年では、海外にも注目されています。普段、ペットボトルのお茶を飲んでいる方も、新茶の季節には、急須で淹れたお茶を楽しんでみませんか?
子どもと一緒に美味しい、温かい新茶を注いで「八十八夜」のお話をされてはどうでしょうか。何気なく飲んでいるお茶にも、昔から伝わる風習がある事を知ると違う楽しみや味わいを持って飲むことが出来るかもしれません。くれぐれも、火傷には気を付けられてくださいね。
八十八夜について、少しでもこのサイトが役に立てると幸いです。
最後まで読んで頂き ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
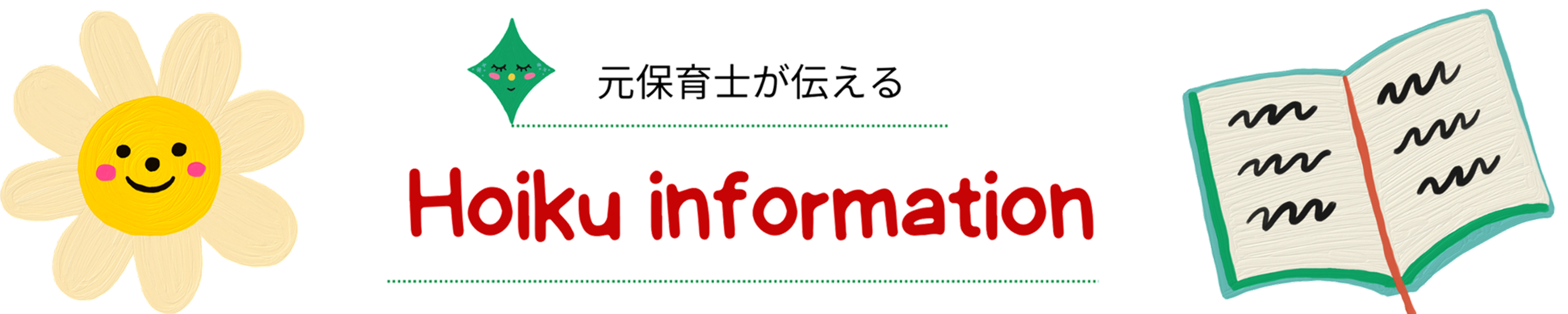


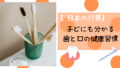
コメント