幼児期において、自分の思いを伝えれるようになると嬉しい反面、子どもが起こす行動において、悩む保護者の方や園の先生も多いようです。私も以前園で働いている時、同じ経験をしていました。
目次
問題行動の奥にあるモノとは
そこで、今回はどうしてそのような行動を起こすのか。起こしたあとの対応の仕方についてまとめてみました。

お集まりの時、ちょっかいを出す子ども
お集まりをしている最中や、説明している時などに隣の友達や、自分の場所から移動して違う場所へ行く子ども、友達からは反発されているけれどちょっかいを繰り返す。
そういった行動をする子どもの気持ちは ”こっちを見て‼ぼくを見て!” と自分に興味を持ってほしいアピールをしているのです。ですが、お集まり最中や、何かしている時には、その子に手を取ることは出来ません。先生は、クラス全体を見ないといけません。そのような状況になったときは
「〇〇くんと、一緒に遊びたんだね。」と一言声を掛けて、共感する気持ちを持って話してあげましょう。そうすると「先生、僕と一緒なんだ」と、子どもは大人と同じように共感されると嬉しい気持ちになります。もちろんその後は、今置かれている状況のお話に戻しましょう。
友達の思いを聞かず、困らせる行動をする子ども
友達の思いを聞かず、自分の思いを一方的に友達に伝えて遊びの中でトラブルになり、保育士から、何度も声を掛けられても止める事なくエスカレートする子どもがいます。
そのような子どもの背景には、“家庭での保護者との関係が、困った行動を起こしてしまう場合”となることがあります。
今の社会にはなくてはならない”スマートフォン”。子どもといる時間に、スマホの画面ばかり見て、子どもが十分に自分の気持ちを聞いてもらえていない事も関係してきます。授乳中、スマホばかりみていませんか?子どもの表情を見ていますか?小さい子どもは、言葉では伝えられないですが、身体全体で自分の思いを伝えているのです。このようなサインを見逃すと、「自分の気持ちを聞いてくれない」と、感じるようになるのです。
幼児の場合、第1反抗期に家庭や家庭以外の社会 (園や学校) に向けて相手の気持ちを理解しようとせず、自分の思いを一方的に伝え大きなトラブルになる時があります。幼児期は、保護者との関係が修復できる時期でもあるので、まず子どもの思いに耳を傾けることから始めるといいと思います。
社会性を学んでいない子ども
乳児期では、保護者や子どもと関わる身近な大人にたくさんの愛を受けて、「聞く」「話す」「行動する」などの基礎的な力の土台を作ります。
幼児期になると、「生きる力」の土台となる大事な時期に入ります。この時期から自我が現れ、人との関わり、信頼関係や、遊びの中で思考力や想像力など育んでくるのです。
その経験をせず年長からの入園や園での経験をすることなく就学すると、人と話すことが出来ない、発達が遅れているなどの問題が見えてきます。その問題に苦しむのは、子どもです。そうならないように幼児期から遊びの中で、友達との関りで学ぶことが必要となってくるのです。。
おわりに
幼児期は「生きる力」の土台となる大切な時期です。「ちょっかいを出す子ども」「困らせる行動をする子ども」「社会性を学んでいない子ども」どれも、身近な大人から起きる行動です。
子どもの気持ちを言葉で表し、「〇〇してほしいの?」「〇〇だったよね」などの共感が、子どもの心を和やかにします。子どもの気持ちのサインを推測することが大切です。
そして、幼児期から色んな事を経験させてあげることをお薦めします。五感(視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚)を通して色んな事を体験すると、「生きる力」の土台となる、思考力、想像力、運動力などの自発性も大いに伸びると思います。
最後まで読んで頂き ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
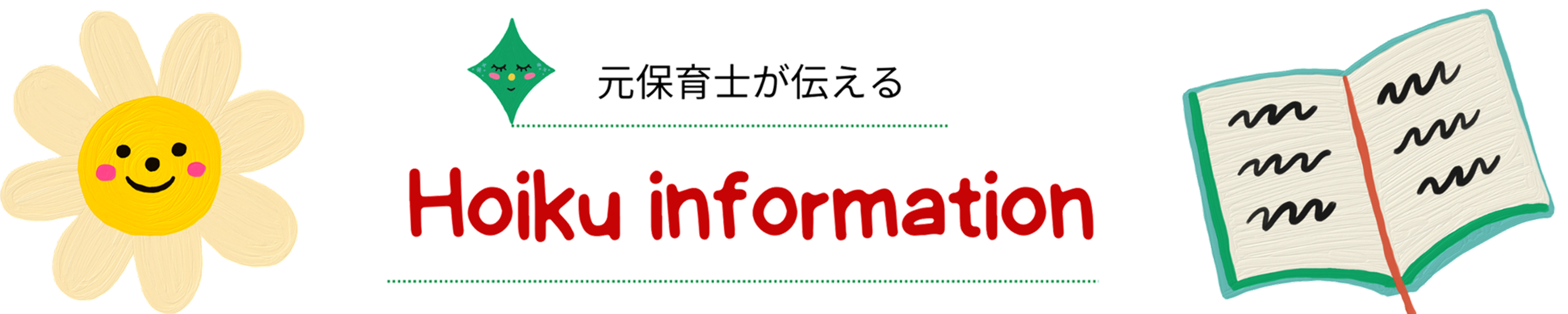

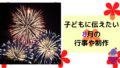

コメント