平成時代前半までは、「保育園は、元気に走り回って遊ぶ」「幼稚園は、お勉強」とのイメージがありました。しかし、共働きの家庭が多くなり子どもに合った質の高い保育を求めたり、将来の役に立つ課外活動をしてくれる園の選ぶような保護者が多くなってきたことから、園などのサービスも多様化されてきています。
ここでは、園においての「勉強」について伝えします。
目次
幼児教育ではどんな「お勉強」をするの?
子どもは3歳くらいまでには、脳の構成が作られるといわれています。3歳くらいになると、言葉を話すようになり、集中して絵本を読んだり、遊んだり、制作などにも取り組む事ができるようになります。この時期から、様々なことを吸収していくのです。
幼い頃に体得したことは、いつまでも変わらない
3歳から、右脳と左脳の力を結びつける大切な時期になります。この時期に吸収したことは、アウトプットしていくのです。人や様々な物との関りを通して、好奇心や思考力が芽生え始める頃となります。色んな経験をしながら、遊びの中で「勉強」を取り入れていくと「できた!」との喜びが、自信となり「生きる力」を育んでいくのです。
園での「お勉強」
今では、保育園と幼稚園が一緒になった「認定こども園」が多く存在するようになってきました。
1号 2号 3号と別れていますが、「お勉強」の内容は全て同じの内容を取り組んでいます。
園において様々ですが、課外教室についてまとめてみました。
| <課外教室> | 年少 | 年中 | 年長 |
| 英語教室 | Ο | Ο | Ο |
| リトミック | Ο | Ο | Ο |
| 体操教室 | Ο | Ο | Ο |
| 学研 | Ο | Ο | |
| プログラミング | Ο |
年少
言葉が徐々に増えてきている3歳児。色んな言葉を覚えるために知育カードを見て名前を答えたり、同じ仲間のカードを集めたりしながら知能の発達を生み出しています。手先を使った、制作やお絵描きなども取り組んでいます。1から10までの数字をしっかりと数えることが出来るようになります。
年中
先生の説明を聞けるようになり、椅子に座って制作に取り組む事が出来るようになります。鉛筆を持って、線をたくさん書きながら、~線や〇線などへ進展し、顔の形が整って描けるようになります。思考力、想像力が膨らみ盛んになってきます。ルールがある遊びの理解も出来るようになります。
年長
集中力が徐々に伸びてきて、30分椅子に座って活動が出来るようになります。鉛筆の持ち方を学び平仮名や数字などを書く練習を始めています。簡単な絵本を、読む習慣を取り入れたりもします。行事の時は、団結して協調性を養い達成感を味わうことが出来ています。友達や他のクラスの友達と関わって遊び、相手を思いやる気持ちを持てるようにもなります。
まとめ
幼児を取り巻く環境の変化によって、園の取り組みも多様化しています。豊かな学びやすい環境の中で、3歳からアウトプット出来るように園では、様々な「お勉強」を取り入れています。発達段階を踏まえながら、繰り返し行うことで基礎的能力を高め、「生きる力」を養っていくのです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
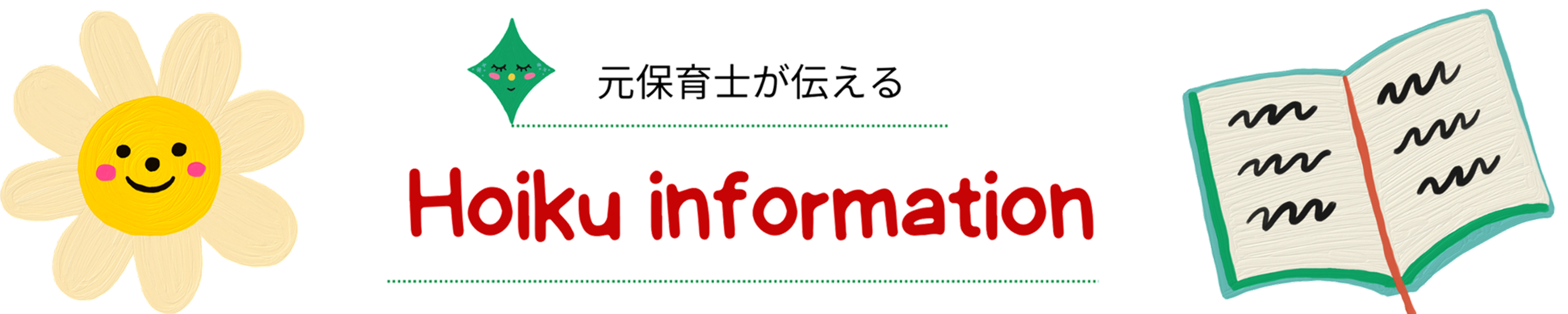

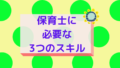

コメント