7月や8月になると、各地で夏祭りが行われています。
町ぐるみで神輿や夜店の準備をしているのを見かけたことはあると思います。夏祭りが近くなると、子どもも大人もワクワクして楽しみですよね。
子どもに、「夏祭りって何?」と聞かれたときに、きちんと答えることができますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるようにここでは、「夏祭り」についてご紹介します。
目次
夏祭りって何?
昔は、梅雨から夏にかけて多くの病気が流行する時期でした。今のように、医学も整っていなかったため、病気が流行することは悪霊の仕業と考えられていたようで、病魔や厄災を祓うためのお祭りだったとのこと。
夏祭り・・・病気や災害をもたらす悪霊を追い払う祭り
夏祭りは、無病息災を願い、五穀豊作を願い労働者を労うなどの意味が込められており、自然災害などを追い払う目的で夏祭りを行う地域もあるそうです。
四季によって違う祭り

日本には、昔から五穀豊作を願う祭りが行われていました。
夏は、病気や災害が多く発生する時期となっていたので「厄除け」
秋は、収穫時期になるので「収穫祭」
冬は、収穫を終えた田を労い新年に向けて「新春祝い」
祭りを行うことには、それぞれの願いが込められていたのです。
霊は賑やかなものにつく

祭りは、たくさんの人が参加して賑やかな時間となります。
それには、理由があったのです。
悪霊は、賑やかなモノに付いていくと言われていた。
そのために、賑やかなお囃子(はやし)が入っているそうです。
祭りの中で、欠かせない屋台や山車(だし)の上で、笛や太鼓、鉦(かね)、鼓(つづみ)などを鳴らすモノ
盆踊り
夏祭りが近くなると、盆踊りの練習をしている音を聞いたりしたことはありませんか?
盆踊りには、お盆に帰ってくるご先祖様の霊を迎える鎮魂(ちんこん)の儀式と言われており、亡くなった方を供養するための踊りです。
祭りの夜はたくさんの夜店

子ども達が、夏祭りの中でも楽しみにしている夜店。
たくさんの催しに、子ども達のワクワクしていますよね。昔ながらの遊びに、大人も嬉しくなりますよね。
地域の名物を堪能したり、購入したりして地域の方々との交流も深めることが出来ます。
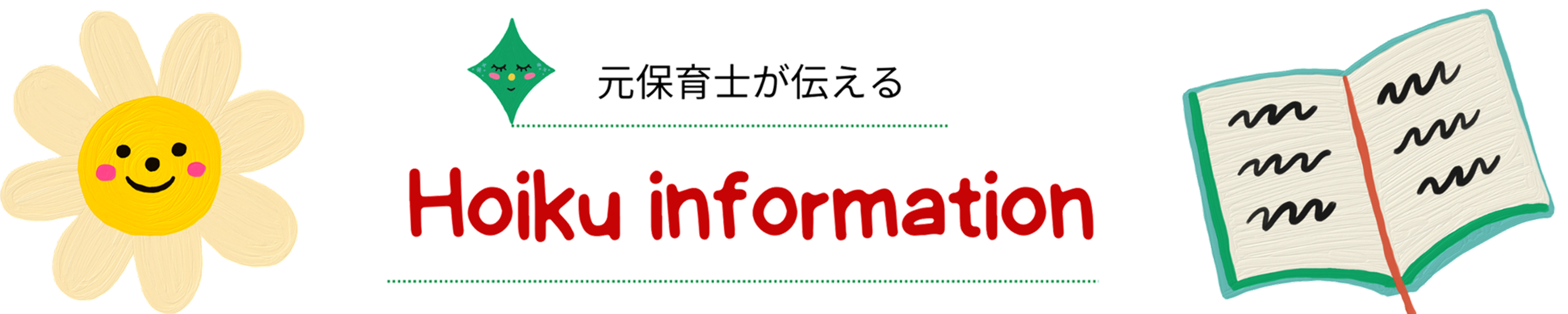



コメント