一年の終わりの大切な日。
1年間の思い出を振り返り、新しい年を迎える前日の大切な一日。
どうして、この一日が大切な日になるんだろう。
子どもに、聞かれたときにしっかりと答えることができますか?
ここでは、昔から日本の風習として受け継がれている大晦日について、子どもにも分かりやすく大晦日の行事について紹介します。
目次
大晦日は毎年【12月31日】
大晦日(おおみそか)は、一年の最後の日のこと。
晦日(みそか)は、月の最後の日を表す言葉。
年の最後の月の日だけ、大の字を付けて大晦日と言うようになったとのこと。
掃納(はきおさめ)をしよう
掃納(はきおさめ)という言葉は、今はあまり聞かれなくなっています。
掃納(はきおさめ)とは・・・
元旦に掃除をすると、福を掃き出すことになるので、掃除はしないほうが良いとされています。そのため大晦日の内に、家の中や家の周りを掃いくことで、新年を心地よく迎えること。
大掃除では、新しい一年を迎えるために屋内、屋外をきれいにすることですが、大晦日の日に、全てきれいにして正月飾りを取り付けることは、1夜飾りとなるため避けた方がよいと言われてます。
大掃除は、煤払い(すすはらい)をする日が良いとされており、12月13日です。
煤払いとは・・・
家の中のすすやほこりを払って、きれいに掃除する事。払うことは、清めること。
昔は、12月13日が大吉とされる日だったため、新年の年神様を迎えるための煤払いは欠かせない行事であり、それが広がったとのこと。
お節料理の準備
お正月に欠かせない物が、お節料理です。お節料理には、それぞれの健康を願う気持ちが込められ、使われる食材にもそれぞれの由来や縁起が良い物ばかりです。
お正月は年神様をお迎えし、新年を迎える大切な日に年神様に振る舞うお節料理には、五穀豊穣、家内安全、子孫繁栄、不老長寿、などの意味を込めた山の幸、海の幸をたくさん、重箱に詰める(箱を重ねる=めでたさを重ねる)といいと言われています。
新年に用意するのではなく、12月31日(大晦日)には、すべて整えて新年を迎えるために、保存のきくような縁起のいい食材をお節料理に入れて作られています。
伝統的な料理に加え、家族が好むお祝いメニューも加えて、お正月ならではの味を用意しておくといいですね。
博多久松 おせち料理は、人気です。
正月の縁起のいい食材が多く入っています。
 |
価格:15,800円 |
年越しそばは、どうして食べるの?
江戸時代から、年越しそばは、新しい年を迎える前に延命長寿の願いであるそばを食べることで、
「そばのように、細長く生きられますように」
との縁起を担いで、大晦日の夜に食べると長生きできると言われていました。
お子様が小さいご家庭では、まだそばを食べたことがないお子様にはそばのかわりにうどんを食べるといいですよ。
除夜の鐘
除夜の鐘とは、大晦日(12月31日)の深夜0時をはさんで、日本各地のお寺でつく鐘のことを言います。
人間には、108つの煩悩があると言われています。
煩悩・・・人の心を苦しませたり、煩わせたりすること
107回の鐘をつくことで、心の中に残っている悩みや嫌な事を取り除き、108回目の鐘で新年が清らかな年でありますようにと、年が明けた瞬間に大きく鳴らされます。

まとめ
子どにも分かる大晦日は、いかがだったでしょうか。
大晦日の日について意味や由来を知ることで、子どもと一緒に新しい1年を清々しい気持ちで迎えることができると思います。
大晦日の行事は、日本ならではの伝統な風習であり、これからの子ども達も残していきたい行事の1つです。
子どもにも分かる説明で、日本の文化を楽まれることを願います。
ご参考になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
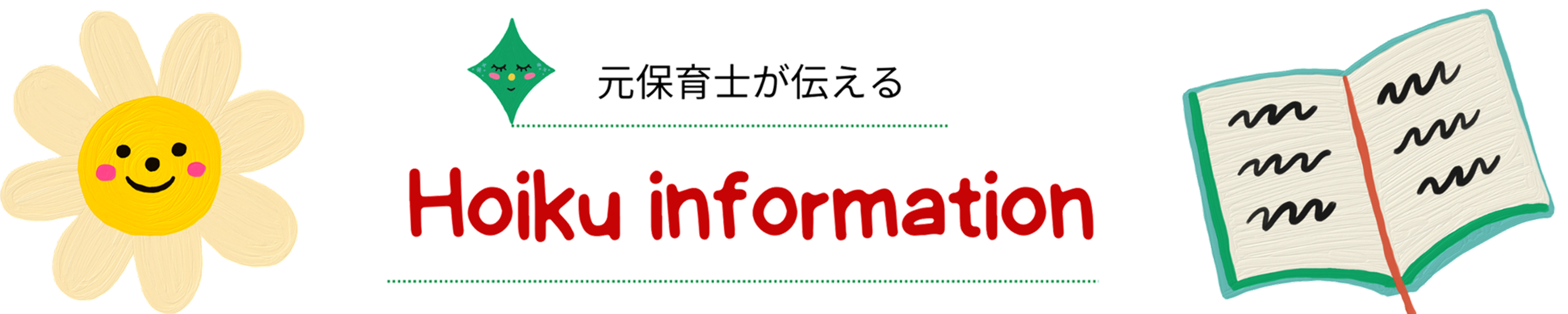



コメント