近年、子どもが自ら考える力が注目されるようになり、自分で考えて答えることの重要性が取り上げられるようになりました。考える=思考力です。子どもが社会に出るころには、AIが普及され自分の考えを表現する力が必要になってきます。
ここでは、子どもの考える力が育つ3つのことについてまとめてみました。
目次
子どもの考える力とは?
子どもが、自分で考える事は難しく考える必要はありません。日常生活において、様々な考える力を持っているのです。普段の遊びの中で、探索しながら「どうすればいいか?」「どうっやったらできるのか?」「できた!」との繋がりを繰り返します。このような、「計画する → 問題が起きる → 問題解決を考える → 解決する 」は、思考力を育んでいるのです。
考える力とは、問題を解決する方法を見つける事。
考える力は、将来自立するための生きる力も身に付いてくるのです。
子どもの考える力を育てるためには、非認知能力が注目されています。
非認知能力とは・・・
自分で行動を起こし友達と関わったり、感情をコントロールすることが出来る力
非認知能力は、日常生活の中で人と関わる事で自然と身に付いてきます。例えば遊びの中で色んな形を積み重ねたり、目標を捉えたりすることから学ぼうとする力=考える力を働かせています。何気ないやり取りの中で、子どもは考える力を養っているのです。
つまり、人との関りから徐々に一人で問題を解決しようとする考える力が育ってくるのです。
考える力が育つ3つのこと
では、どのようなことをすると考える力が育つのでしょう。
ここでは、考える力が育つ3つのことについてまとまてみました。
考える力が育つには、人との関り、思いやり、好奇心です。
人との関り
日常生活において、子どもは身近な大人との関りの中で成長していきます。考える力は、与えるものではなく人とのコミュニケーションの中で育ってきます。人との関りの中で、会話を楽しみ自分に問い、相手へ伝えるやりとりも考える力が育ってくるのです。また人との関わりの中で様々な体験をすることから、どうしたらいいいんだろう?と思うことから始まるのです。大人は子どもが自発的に考えて、探索心を持ち始めることを見守り、自ら考えて行動することを支えてあげましょう。そうすることで思考力を養うことが出来ます。
思いやり
どの社会においても、相手の事を思いやりが不可欠です・・・人の考えを想像する考える力をもつことで、自分以外からも物事を考えることが出来ます。相手との比較をしながら共通点、相違点を発見し、自分の意見も主張することが出来るのです。
好奇心
好奇心を持っていないと、「どうして?」「なぜ?」と疑問を持って物事を考えることが出来ず、考える力を持つことが出来ません。自己肯定感が弱くなり、自分に自信が持てず人の意見をうのみにしてしまいます。
好奇心を持っていると、遊びの中でも探究心が芽生え、疑問に持ったことを、解決しようと行動に移すことが出来ます。例えば、ブロック遊びをしている中で、ロボットを作るためにはどうやってブロックを積み重ねるといいのか?こうではない。こうかな。など何度も挑戦して思い描いた物を完成させまます。そして、また違う形を作り始める。このような取り組みの中で、好奇心は育ち行動力や集中力も養われてくるのです。
まとめ
考える力が育つ3つのことはいかがだったでしょうか。
考える力は、日常生活のコミュニケーションの中から身に付いてくるのです。教育中でも、思考力が大きく関わってきています。時代の変化と共に、必要になってきている子どもの考える力。これまでは、教科書通りに行っていた認知能力から、自分で見つけ考える力が必要となってきている社会。
子どもの考える力を付けるためには、人との関りを通してたくさんの会話と楽しめる遊びや、体験をして、思いやりや色んな好奇心を持つことが重要となってくるのです。
子どもの、興味や関心を高めて色んなことを体験させて考える力を育ててください。
最後まで読んでいただき ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
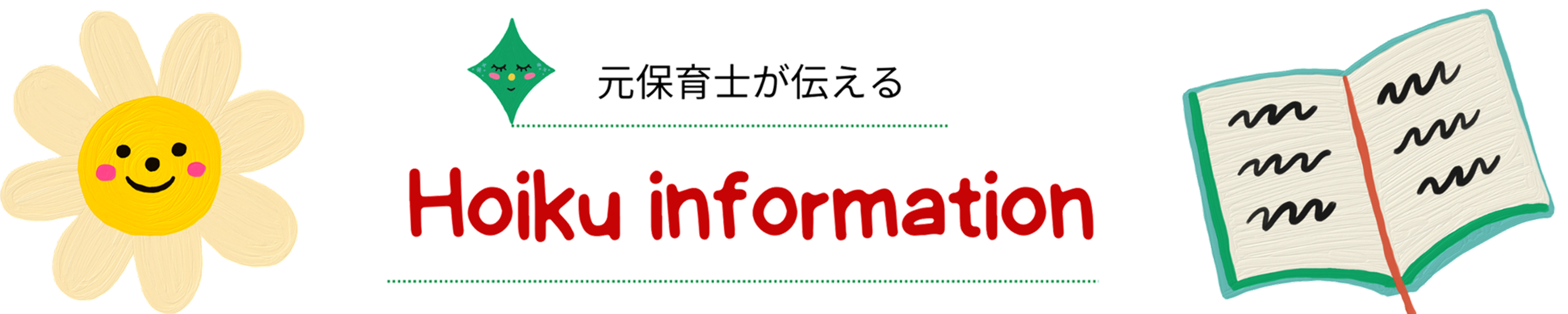

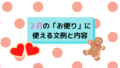
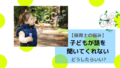
コメント