お正月遊びと言えば、、日本伝統の凧揚げや羽根つき、駒回しなどが浮かびます。昔から伝わる伝承遊びには、様々な思いが込められています。
伝承遊びは子ども達が考えた遊びなので遊びやすいですが、新しい先生の中には、実際に遊んだこと経験したことがない先生も多くいました。
社会の変化に伴い、親から子へ受け継がれることが少なくなってきた伝承遊び。だからこそ、保育園や幼稚園やこども園で伝えてあげることで、次の世代に引き継がれていくことが出来ます。
ここでは、子どもが楽しめる正月の伝承遊びについてまとめてみました。
目次
正月伝承遊び
お正月遊びは、世代を超えて楽しめる遊びがたくさんあります。新しい年の始まりと共に、身体を使ってたくさん遊び笑いながら過ごすことが出来ます。
正月の伝承遊びは、子どもの健やかな成長と共に願いが込められている遊びもありますので参考になると幸いです。
凧揚げ

♪た~こ~た~こ あ~がれ~♪と歌いだす、子どもの声は凧揚げをしているかのように響いています。現代では社会の変化に伴い、凧揚げできる場所は限られ、凧揚げをしている風景は見られなくなりました。ですが、正月遊びの中で、凧揚げは子ども達に人気の遊びなのです。
<由来>
中国では凧揚げは戦いの道具の1つだったとのこと。
日本では江戸時代から、男の子が誕生したら凧を揚げてお祝いするようになったとのこと。
凧が高く上がるほど、元気に育つと願いが神様に届くと言われていたとのこと。
<遊び方>
広い場所でに、凧を高く空に向けて揚げたり、凧が長く上がっている時間を競ったりする。
小さい子どもは、長い紐を操ることは難しいので、スーパーのビニール袋に絵を描いて、50㎝ぐらいの紐を付けて持って凧揚げをして楽しむのもいいです。
羽根つき

昔は、女の子の初正月に羽子板やてまりを贈る風習があったとのこと。
中国で、羽に硬貨をつけた物で遊んでいたことが日本にも伝わり、羽子板→こきいたと呼ばれていたそうです。羽根は、無患子(むくろじ)という植物の種が使われ「子供が患わない(わずらわない)=子どもが病気にならない」と言われ魔よけに通じる縁起がよいとされていました。
羽根つきは1年の厄をはね、子供の健やかな成長が長く続きますようにとのこと。
顔に黒い炭を塗ることは、鬼が嫌がる黒を塗ることで魔よけの意味があるとのことです。
<遊び方>
1人で遊ぶ場合は、つき羽をして楽しみ、2人でする場合は追い羽をして楽しみ、羽を落としたらか顔に墨を付けていく遊びがあります。
子ども達は、数えながら遊ぶことで数字にも興味をもてるようになります。
駒回し

駒回しはエジプトから、唐(韓国)から高麗(朝鮮)へ渡り日本に奈良時代に来たと言われています。昔は、貴族の遊び道具だったけれど江戸時代に、庶民の遊びとして受け継がれてきたそうです。
物事が円滑に回るに通じて縁起がよく、うまく回ると子どもが早く独り立ちできるとのこと。
韓国の唐から高麗(朝鮮)を経て日本に来た「こま」。以前、高麗(こうらい)は「こま」と呼ばれていたので、「こま」と呼ぶようになったとのことです。
<遊び方>
駒の持ち方や紐の巻き方など、独特な駒回し。巻いた紐を引き出し、駒の回転を楽しんだり、長く回して競い合ったり、駒をぶつけて競ったりする。
子どもは、大人と一緒に経験しながらコツを掴んだり、紙や自然植物などで作った駒回しを楽しむこともオススメです。
お手玉

平安時代に石を使った「石なご遊び」から、袋の中に小豆や大豆を入れた遊びへと進展したそうです。
「石なご遊び」・・・石をまき、その中の一つを投げ上げておいて、下の石を拾い、落ちてくる石をつかみ取って、順に拾い尽くす遊び。
<遊び方>
まずは、1個投げて受け取る。それが出来るようになったら、左右1個ずつ持ち、片方投げて同時に投げ上げて、捕る。これを連続して慣れてきたら、お手玉を増やしていく。
福笑い

目隠しをして、輪郭の紙にパーツを置いていくと笑いがあふれます。
笑う門には福来るとのこと。
新年から、たくさんの笑いがこぼれるとめでたいと言われ、正月遊びにふさわしくなったそうです。
<遊び方>
目隠しをして、輪郭を描いた紙の上に、顔のパーツを置いていく遊び。目隠しをする時、タオルで巻いていましたが今は、便利な目隠し(アイマスク)が販売されています。
子ども達で、パーツを描いて作りそれを楽しむこともオススメです。
すごろく

昔は、将棋のように二人で遊んでいた遊びから、サイコロを使うようになったそうです。
すごろくをすることで、その年の運試しの楽しさも味わえるとのこと。
旅や人生にちなんだ「道中双六」や「出世双六」のような「絵すごろく」が人気を呼んだそうです。
<遊び方>
サイコロが出た数だけ進み、立ち止まったマスの仕掛けを楽しむ遊び。早くゴールした人が勝ち。
子ども達で、すごろくの絵を描き、仕掛けを描いて楽しむこともオススメです。
けん玉

世界各地で遊ばれているけん玉は、昭和時代に子どもの遊びで流行したそうです。
玉の赤色はご来光を思わせるめでたいものとのこと。
けん玉は、平衡感覚が重要となる身体全体を使う遊び。
<遊び方>
大皿の上に玉をのせたり、左右にのせたりする遊び。慣れない子どもは、まずは手のひらサイズのボールをポンポンと投げて、膝を曲げて捕る感覚を覚えることから始めるといいです。
百人一首

室町時代にポルトガルから伝わったそうです。日本では、トランプを模倣した「天正カルタ」と呼ばれる物が最初に作られました。しかし、博打(金品をかけて勝負したりすること)に使われていたので、幕府から禁止されたそうです。
その後から「天正カルタ」がヒントになり、百人一首・花札・いろはカルタになったとのこと。
<遊び方>
読む人と取る人に分かれ、並べたカードの読み札に合ったものを取る遊びで、多く取った人が勝ちという遊びです。
ダルマ落とし

♪だ~るまさん だ~るまさん♪と子どもに人気なわらべうたでお馴染みのダルマさん。元は、天竺(てんじく=インド)から中国に渡り、お釈迦様の正しい教えを日本に伝えられたとのことです。菩提達磨大師(ぼだいだるま)が今日の禅宗の礎となっています。
ダルマを落とさず(倒さず)に成功すれば縁起がいいと言われていたとのこと。
ダルマは、転んでも起き上がるけれど、ダルマ落としのダルマは転んだら起き上がれないために落とさないようにして願掛けをしながら遊んでいたそうです。
<遊び方>
積み重なった積み木の一番上にあるダルマを落とさないように、ダルマより下の部分の積み木を叩き落としていく遊び。コツは、水平に素早く叩くことです。
まとめ
正月の伝承遊びは、子ども達にとっては新鮮な遊びだからこそ、目を輝かせて遊ぶことが出来ます。昔から受け継がれている遊びを保育の中で取り入れながら、新しい遊びを見つけることが出来るかもしれません。
次の世代を生きる子ども達に、日本の伝承遊びが風化しないように伝えていけると嬉しいです。
最後まで読んでいただき ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
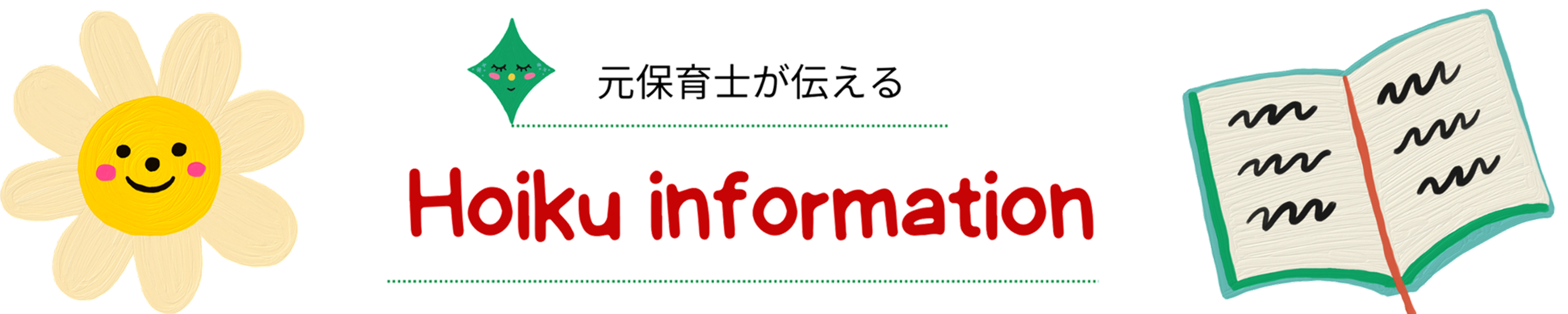


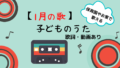
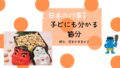
コメント