2月11日は、国民の祝日「建国記念の日」。「建国記念日」と間違える人も少なくないかもしれません。
子どもに、「建国記念の日って何?」と聞かれたときに、しっかり答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるようにここでは、「建国記念の日」についてご紹介します。

目次
建国記念の日について
2月11日は、建国記念の日。
1966年2月11日に日本の初代天皇である神武天皇(じんむてんのう)が即位した日を「建国記念の日」と制定したとのこと。
日本という国が正確に出来たのかはわかりません。
建国記念の日は「日本の国が出来たことをお祝いする日」
建国記念の日に「の」が入るわけ
1966年に「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として、建国記念の日が制定されました。
建国記念の日に「の」が入っている理由は、「建国をしのび、国を愛する心を養う」日であるとされており、建国した日を祝うのではなく、建国された日本の国を祝う日とされているからです。
日本の国を知ろう

建国記念の日とは、日本の国が出来たことをお祝いする日。
日本の国旗を、「日の丸」と呼ばれることが多いですが、正式には「日章旗」だそうです。
赤い丸は、太陽の意味が込められていたり、日本では紅白がめでたい配色とされいることからとも言われています。
日本国旗は、子ども達が描きやすいので記念に描いてみることもいいですね。
我が国に感謝しよう

日本には、たくさんいい所があります。
建国記念の日は、日本という国が出来た日を祝い、みんなで大切にしようとする気持ちを育てたいですね。
次世代を担う子どもたちに、日本の歴史を伝えながら国を愛してほしいと願います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
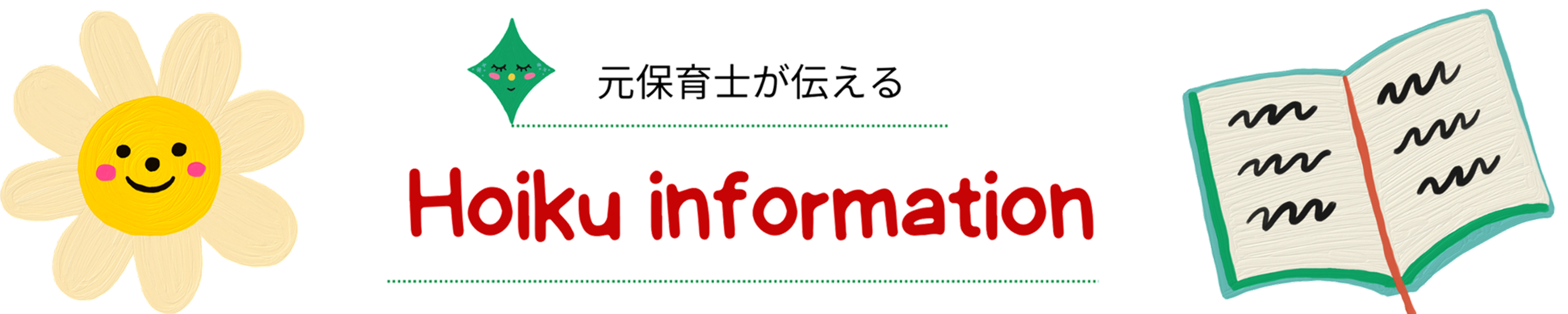



コメント