古くから日本は、行事を大切に執り行っていました。
年末になると、新年を迎えるために家の中を片付けたり、準備をしたりと忙しく過ごされる方もいるのではないでしょうか。
ここでは子どもに、「大掃除はなんでしないといけないの?」と聞かれたときに、きちんと答えることが出来ますか?
これからの時代を支えていく平成、令和時代の子ども達へ、しっかりと意味を伝えられるように、「大掃除」についてご紹介します。
目次
大掃除とは

新年の歳神様を迎えるにあたって、大掃除をすることです。
大掃除が終わると、次は年神様を迎える準備をして家の外や中に正月飾りを飾ります。
煤払い

昔の生活に欠かせなかった、囲炉裏やかまど。その囲炉裏や、かまどに溜まった1年の汚れを払い、清めることを「煤払い(すすはらい)=大掃除」と言っていました。
煤払いすることで、新年に訪れる年神様がたくさんのご利益を持って下りてこられると言われていたそうです。現代の家庭では、煤払いと無縁の方が多いですが、今でも神社やお寺では煤払いの行事が盛んに執り行われています。
大掃除は、12月13日。
旧暦で、婚礼以外は万事に大吉とされる日だったため、今でもその日にすると、いいと言われています。
しかし、実際には1日だけでは難しく掃除を終わらせることが無理な方も多いので、家庭で決めて取り組まれています。
年神様を迎える準備

大掃除は、お正月に年神様を迎えるための神事として執り行われていました。家の中に、たくさんのご利益を頂くために、1年の煤を払い清め、穢れを祓う意味もあるそうです。
年神様を迎える準備は、大掃除だけではなく鏡餅や、門松、しめ縄、お節料理などがあります。
大掃除はみんなでしよう

大掃除は、昔は「煤払い」と言われ執り行われていたことだと、お分かりになったでしょうか?師走の忙しい時期ではありますが、年神様を迎え入れ、たくさんのご利益を頂くためには、欠かせない行事なのです。
みんなで協力して掃除を執り行い、1年の厄を払い感謝し、新年を気持ちよく過ごされてくださいね。
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
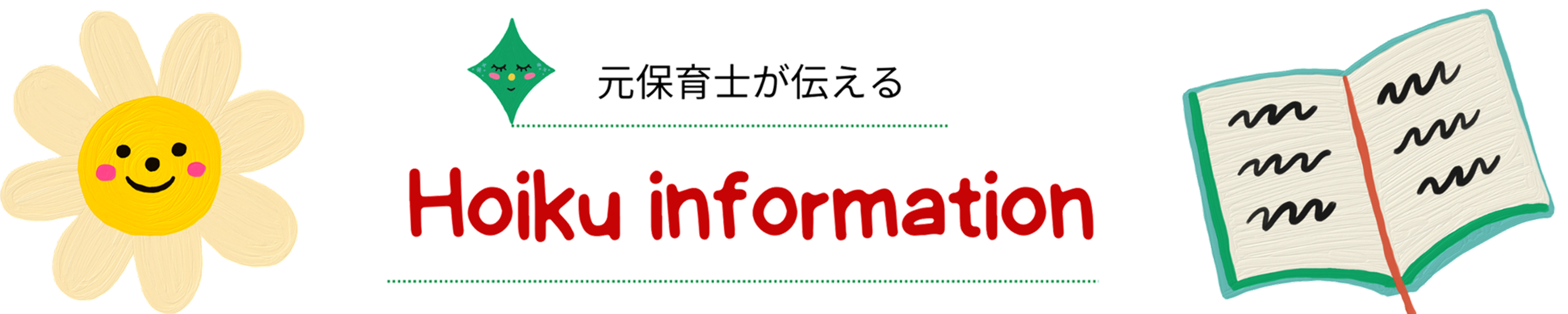



コメント