日本には、古くから数多くのの「わらべうた」が歌い継がれてきました。
「いっぽんばしこちょこちょ」「かごいちもんめ」など、
小さい頃誰もが1度は耳にしたことがあると思います。
子どもが遊びながら、言葉のリズムを取り入れることが出来たり、体を動かすことでスキンシップが育まれる「わらべうた」には、乳幼児期にに必要な要素が隠れています。
今回は、わらべ歌について紹介しますので、子どもと関わる方への参考になるといいです。
目次
わらべうたとは?
童歌(わらべうた)・・・昔から伝えられ子ども達の間で歌われてきた歌。
童歌は、伝承童謡(でんしょうどうよう)や自然童謡(しぜんどうよう)とも言う。
昔の子どもたちは気持ちを伝える時、言葉ではなく歌や踊りで表現していました。そこから「わらべうた」が誕生したそうです。
子どもが自然に歌いやすい音階で作られており、子どもに馴染みやすい音楽です。
今では、「リトミック」が普及されていますが、「わらべうた」もリトミックと同じような
働きがあるのです。
コミュニケーションを育む
わらべうたは、子どもにとって歌いやすいメロディーであり、リズムに言葉を載せながら、手足や身体を加えた動きが取り入れてあります。視線を合わせて一緒に楽しむことは、コミュニケーション能力を身に付けていくことが出来るのです。
乳幼児期は、大人の方と1対1で向かい合って、子どもの顔に身体に触れながらスキンシップをとり、徐々に「聞く」「見る」「発する」などと言葉と動きを覚えていくことが出来ます。
幼児期は、1対1から集団での「わらべうた」を取り組むことが出来るようになっていきます。友達と協力しながら一緒に歌い、動き、息を合わせることで協調性を育み楽しみながら、社会性を身に付けていきます。
日本の自然や心、地域の文化を感じる
わらべうたは、日本人が言葉にして気持ちを伝えた歌であります。
昔から自然を大切にする日本人ならではの言葉もあり、自然に対する思いを感じさせられます。
日本の四季折々の風景を口ずさむことで季節を感じたり、各都道府県ならではの様子を感じたりすることが出来ます。
リズム感や運動能力が養われる
わらべうには、「触れる」「揺れる」「動く」「叩く」「掴む」などの要素が多く含まれており、道具も場所もいらずに、身体だけで表現できる遊びです。このような動きは、子どもの身体感覚を育てることが出来るのです。
日常生活における基礎が身に付く
わらべうたには、さまざまな言葉が含まれており、生活の基礎となる役目もしています。わらべうたを歌うことで、自然と言葉を覚えていくことが出来ます。また、数え歌や絵描き歌は、数字や描くことの楽しさも教えてくれるのです。
乳幼児期はわらべうたを楽しもう
わらべうたは、日本人にとって多くの方が1度は耳にしたことがある曲が多く存在します。
伝承童謡、自然童謡とも言われている「わらべうた」には
- コミュニケーション
- 日本の自然や心、文化を感じる
- リズム感や運動能力が養われる
- 日常生活の基礎が身に付く
このように、子どもに必要な要素が含まれています。
わらべうたを楽しむ中で、スキンシップや社会性を学び、日本各地の文化を知ることで、そこの地域の名称を覚えたりすることも出来ます。
昔から受け継がれてきている「わらべうた」。これからの子ども達にも、たくさんの「わらべうた」をきかせてあげていきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。
*ポチッ*としていただけると嬉しいです。
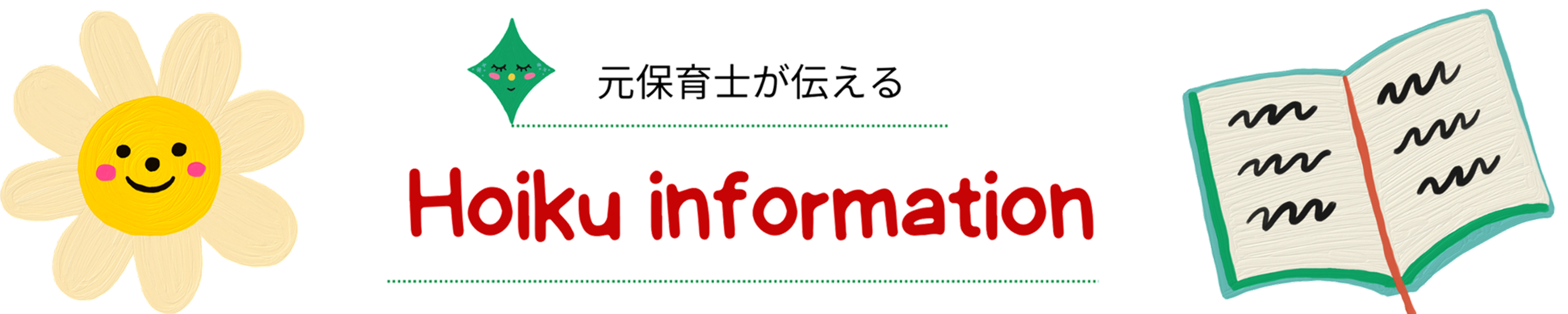




コメント