幼児教育の重要性が大きくとらえられるようになってきました。
子どもが大きくなるころには、AIが今よりも盛んになり「非認知能力」の影響が重要となります。ここでは、子どもに必要な「非認知能力」の必要性について説明していきたいと思います。
目次
非認知能力って何?

先生、今日ブロックで遊んでいい?

今日も、ブロックで遊ぶのですね。色んな形作って楽しんでね。
このように、遊びの中で色んな形を積み重ねたり、目標を捉えたり、友達と協力しながら作ることから、協調性・想像力・思考力などが養われていきます。勉強のように問題を解いて測れる力ではなく、自分で思い行動を起こし友達と関わったり、感情をコントロールすることが出来る力を非認知能力と言います。
非認知能力で得ること
- 頑張る力(忍耐力、志向力、持続力)
- 関わる力(協調性、リーダー、対話)
- コントロールする力(感情、自制心、、客観性)
非認知能力は、どうやって学ぶ?
非認知能力は、3つの要素で学ぶことが出来ます。
- 身近にいる保護者や大人
- 子どもの生活や環境
- 遊び
では、どのようなことなのかを順番に紹介します。
子どもの身近にいる大人との関りで、信頼関係が育まれ、自分の気持ちをコントロールすることが出来るようになるのです。子どもの行動に共感を持つことで、子どもは自分の行動に共感された喜びを感じ、他者に対しても同じように行動が出来るよになります。自発的に取り組む事は、自己肯定感を養い、目標を生み出し協調性やリーダー的存在へ導いていくのです。
「これで遊んで」と、言うのではなく自ら遊びたいと行動することから、意欲を持てるようになります。遊びの中で、探索しながら「どうすればいいか?」「どうっやったらできるのか?」「できた!」との繋がりを繰り返します。このような、「計画する → 問題が起きる → 問題解決を考える → 解決する 」は、忍耐力や思考力、想像力を育むことが出来るようになり「生きる力」を養うことが出来るのです。
園では、どのように取り組むべきか?
園における非認知能力は、どのように学んでいくといいの?と思われる先生もいるかと思いますので、いくつかまとめてみました。
自ら遊びたいと思える環境を作る
決まった玩具を用意するのではなく、子どもが遊びたいと思う玩具で遊べる環境を作りましょう。子どもが、遊びたい。学びたい。と思える素材を、子どもが届く範囲に用意してあげることは、子どもの非認知能力を大きく育てます。子どもが興味を持った玩具の探索心を共有し、やってみようと追及する姿は、生きる力を養うことが出来ます。
子どもに寄り添う
子どもの表情を観察し、子どもの気持ちに共感することが大切です。子どもが怪我したら「痛かったね」と伝えるだけでも、子どもは「痛い事が分かってくれる」と安心し信頼関係が作られてくるのです。また、物事に挑戦する子どもの姿を応援し、頑張れば出来る事を先生自身が子どもと一緒に体験することで、運動会、発表会などやり遂げる力が身に付いてきます。
自然に触れる
自然には多くの非認知能力をが潜んでいます。子ども達に、自然と触れる事で季節の変化と共に変わる植物や昆虫に興味を持ったり、肌で感じたりすることが出来る場所であり、自発的に行動を起こすことが出来るようになるのです。
生きる力に必要な非認知能力
非認知能力は、生きる力を養うには必要不可欠です。遊びの中で経験し、その経験から深めること、何より楽しむことが、好奇心や思考力を育むことが出来ます。
「計画する → 問題が起きる → 問題解決を考える → 解決する 」
これを繰り返すことで、楽しみ、精神力や思考力が身に付きます。このような能力を高めることで、粘り強さを得ることで認知能力の勉強も出来るようになるのです。
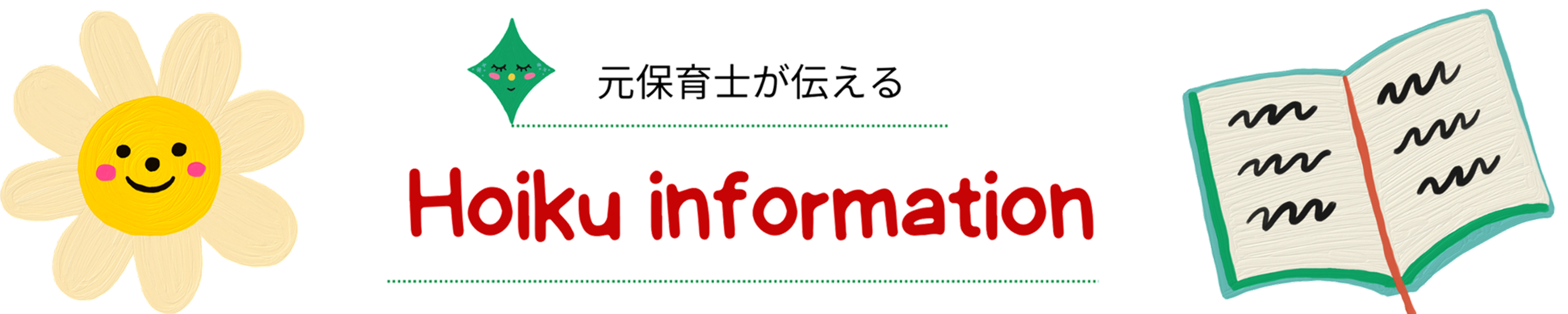



コメント